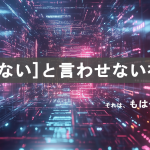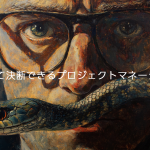「バッファ」の真意を探る
見積りや作業スケジュールの提示の際、エンジニアやシステム会社から「バッファを設けています」という回答を受けることがあります。このバッファという言葉の裏には、予期せぬ事態への保険的な意味合いが込められています。
実際のところ、多くのシステム会社がバッファという言葉を使用する際、それは単なる保険として捉えているケースがほとんどなのです。
バッファが示す不確実性
非エンジニアの立場からすると、見積りにバッファが含まれているという説明を受けた際、それは無駄な余裕ではないかと疑問を抱きがちです。「念のため」という言葉で説明されるバッファの存在は、裏を返せば、十分な知識や経験がないために調査が必要であり、その不確実性への不安から生まれているとも解釈できます。もし十分な知識と経験があり、「念のため」という配慮が不要であれば、そもそもバッファを設定する必要はないはずです。
バッファと見積りの逆説
システム構築プロジェクトにおいて、興味深い矛盾が存在します。それは、バッファの量が多ければ多いほど、実は知識や経験の不足を示唆している可能性が高いという点です。つまり、十分な知見がないにもかかわらず、見積りの総額が高くなってしまうという状況が発生するのです。
このような観点から見ると、「バッファ」という言葉は「無駄な余裕」というネガティブな印象を与えかねません。この矛盾は、プロジェクトの本質的な課題を浮き彫りにしているとも言えるでしょう。
バッファの真の意義
ここで、バッファの本来あるべき姿について考えてみましょう。特に、最先端の技術を活用する場合や、これまでに経験のない新しい領域に挑戦する際には、実際に取り組んでみなければ正確な所要時間が把握できないことがあります。このような状況において、未知の要素がプロジェクトスケジュールに与える可能性のある影響を考慮し、適切な期間を設定することこそが、本来のバッファの意義といえます。
つまり、バッファとは単なる余裕ではなく、イノベーションを実現するための重要な要素なのです。
まとめ
一般的なシステム構築プロジェクトにおいて、無駄を省くという考え方は、非エンジニアの視点からすれば合理的であり、コスト削減にもつながります。しかし、研究開発分野においては、一見無駄に見える要素を排除することが、必ずしも望ましい結果をもたらすとは限りません。それは、余裕の削減が新たな発想の機会を奪うことにもなりかねないからです。
無駄がシステム会社の利益という発注者側との相反関係が、システム会社においてよくある事実ではないかと思います。しかし、この無駄を発想のためのバッファにするためには、現場とエンジニアを理解し、適切に判断できる第三者が必要かもしれませんね。
そんな事業仕分けに興味があれば、アタラキシアDXを思い出してください。いい仕事します!